障害物ゲームで見た「学びのプロセス」
先日、小学3年生と小学1年生の子どもたちと一緒に、ある企画展へ出かけました。
そこで出会ったのが、ちょっとユニークなゲーム。
自分の影を使って操作する障害物競走のようなもので、影が映像内の障害物に触れると「ゲームオーバー」になるという仕組みです。
最初は、どう動けばいいのか分からず、すぐに失敗してしまっていた子どもたち。
でも、何度か挑戦したり、他の参加者の動きを観察したりするうちに、段々とコツを掴んで、クリアできるようになっていきました。
「こう来るから、しゃがもう」「次はジャンプだ!」などと先を読みながら取り組む姿は、とても楽しそうで、夢中そのものでした。
勉強とゲーム、どこが違う?
そんな様子を見ていて、ふと感じたことがあります。
勉強も、ゲームと同じように“挑戦”と“クリア”の積み重ね。
でも、なぜか勉強の方は「つまらない」「後回しにしたい」と感じがちです。
けれど、ゲームになると、子どもたちは繰り返し挑戦し、失敗を糧にしながら上達していきます。
この差って、一体なんだろう? そう考えた時に思い浮かんだのが「ゲーミフィケーション」という考え方でした。
タブレット学習や英語教材にも広がるゲーミフィケーション
実際、近年ではタブレット学習などでも、ゲーム感覚で学べる教材が増えています。
たとえば英語学習では、アニメのような世界観で楽しく進められる「マグナ」などが人気です。
私たちが子どもの頃は「石の上にも三年」「忍耐こそ美徳」といった、いかにも根性論で学ぶことが良しとされていたように思います。
ですが、楽しみながら、自然と身につく学びのスタイルの方が、記憶にも残りやすく、長期的な力になるのではないかと感じています。
学習漫画も立派な知識の種になる
我が家では、日常的に学習漫画を読める環境を整えています。
漫画を楽しく読んでいた結果、「あ、それ知ってる!」となるのは、まさに「門前の小僧習わぬ経を読む」ような自然な学びの形ではないでしょうか。
楽しみながら得た知識が、のちに学びの土台になることを期待しています。
AI時代に求められるのは?
これからの時代、たとえAIがどれだけ発達したとしても、「自分自身の頭の中にある知識」や「個人的な興味・関心から得た情報や経験」が、思考や創造の出発点となるのではないでしょうか。
単なる暗記や詰め込みではなく、興味や好奇心に基づいて蓄積された知識や体験を組み合わせることでこそ、新しい発想やオリジナリティが生まれ、それがこれからの社会で求められる力になっていくと思っています。
一緒に体験できる時間を大切にしたい
そして何より、子どもたちと一緒に出かけてくれる時間には、限りがあります。
親として、今しかできない体験や経験を、できるだけ一緒に味わいたい。
楽しさの中に学びがあるような、そんな場面を、これからも大切にしていきたいと強く思います。
ここまで読んでくださってありがとうございます。
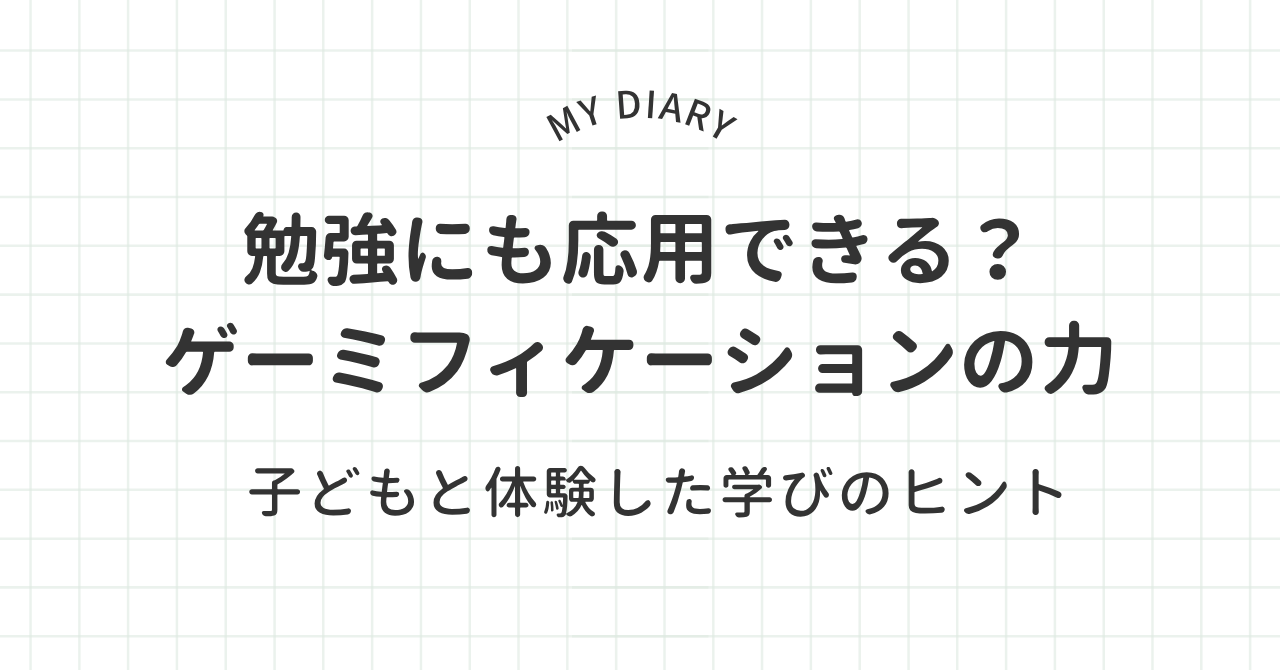
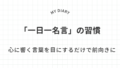

コメント